いつまで腕で引くつもりだ?
懸垂を始めたばかりの頃、ベルはこう思っていた。
「腕さえ強ければ回数は伸びるだろう」と。
でも現実は違った。
腕ばかりを酷使して、前腕と二頭筋がパンパン。
背中はほとんど刺激を受けていない。
その結果、3回で握力が死に、5回が限界。
いわゆる 「腕引き懸垂」 にハマっていたわけだ。
これは懸垂初心者が必ず通る道。
だが、この癖を抜け出さない限り、10回への道は永遠に開かれない。
懸垂は背中種目である
まず大前提として、懸垂は「背中種目」だ。
腕の力で体を持ち上げるものではない。
- メインで使うのは広背筋
- 補助で上腕二頭筋・前腕
- さらに僧帽筋下部や大円筋まで動員する
つまり「体を引き上げる」のではなく、
「背中で肘を引き下ろす」 という感覚が正解なんだ。
この意識が持てないと、いくら頑張っても腕トレで終わってしまう。
背中を使うための意識ポイント
1. サムレスグリップ
親指を外して握るサムレスグリップは、腕の余計な力みを抑えてくれる。
ベルもこれに切り替えてから、背中に刺激が入りやすくなった。
2. 胸をバーに近づける
「顎を上げる」ことをゴールにすると、首や腕が主役になる。
「胸をバーに当てに行く」イメージでやると、自然と背中が動員される。
3. 肩甲骨を寄せて下げる
懸垂は肩甲骨の運動だ。
下げる→寄せる→胸を張る、この3つをセットで意識する。
ダンベルで背中を感じる練習法
懸垂だけで背中を使う感覚を掴むのは難しい。
そこでベルが勧めるのは、ダンベルを使ったシンプルな背中トレだ。
ダンベルローイング(片手)
- ベンチや机に片手・片膝をついて姿勢を安定させる
- ダンベルを持った手の肘を後ろに引く
- このとき「腕で引く」ではなく「肘で背中を寄せる」意識を持つ
広背筋がギュッと収縮する感覚を覚えられる。
ベルはこれを徹底的にやり込んだおかげで、懸垂で背中が動員できるようになった。
ダンベルシュラッグ
- ダンベルを両手に持って立つ
- 肩をすくめず、逆に「肩甲骨を下げる」意識で持ち上げる
僧帽筋下部を使う感覚が養われ、懸垂時の肩甲骨コントロールに直結する。
ダンベルプルオーバー
- ベンチに仰向けになり、両手でダンベルを持つ
- 腕をやや曲げたまま、頭の後ろにダンベルを下ろす
- 胸を張りながら元に戻す
胸と背中を同時に伸ばす動きで、広背筋をダイレクトに感じられる。
「背中が伸びて縮む」感覚を養うには最適だ。
背中を感じるための小技
- ラットスプレッドのポーズを練習する
鏡の前で広背筋を広げる練習をすると、筋肉の存在を意識できる。 - 軽めの懸垂をゆっくりやる
スピードを落として「背中に効かせる」意識を持つ。
こうした小技を積み重ねると、「腕引き懸垂」から「背中懸垂」へ進化できる。
ベルの体験談
ベルはあるとき気づいた。
「懸垂してるのに、二頭筋ばっかり筋肉痛だな」と。
そこで思い切って腕を意識するのをやめ、ダンベルローで“肘で引く”練習を繰り返した。
すると懸垂でも、次の日に広背筋がバキバキに筋肉痛になった。
これが“背中を使った懸垂”の最初の成功体験だった。
そこからは回数も自然に伸びていった。
3回しかできなかった懸垂が、背中を使えるようになった途端に5回、6回と増えていったんだ。
まとめ|背中を使え
懸垂は背中の種目だ。
腕で引く限り、回数は伸びないし、背中も大きくならない。
- サムレスグリップで腕の力を減らす
- 胸をバーに近づける意識
- 肩甲骨を寄せて下げる
- ダンベルロー・シュラッグ・プルオーバーで背中感覚を養う
これらを実践すれば、懸垂は“腕トレ”から“背中トレ”へと進化する。
そして、その瞬間から10回への道が見えてくる。
次回は「食事と体重管理が懸垂を決める」というテーマでいこうと思う。
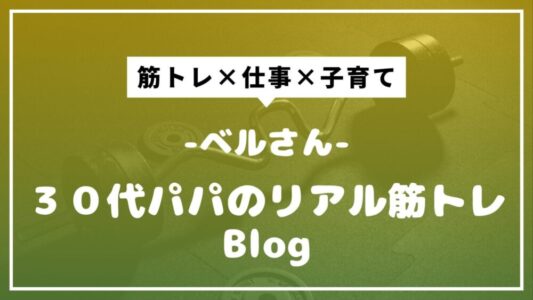
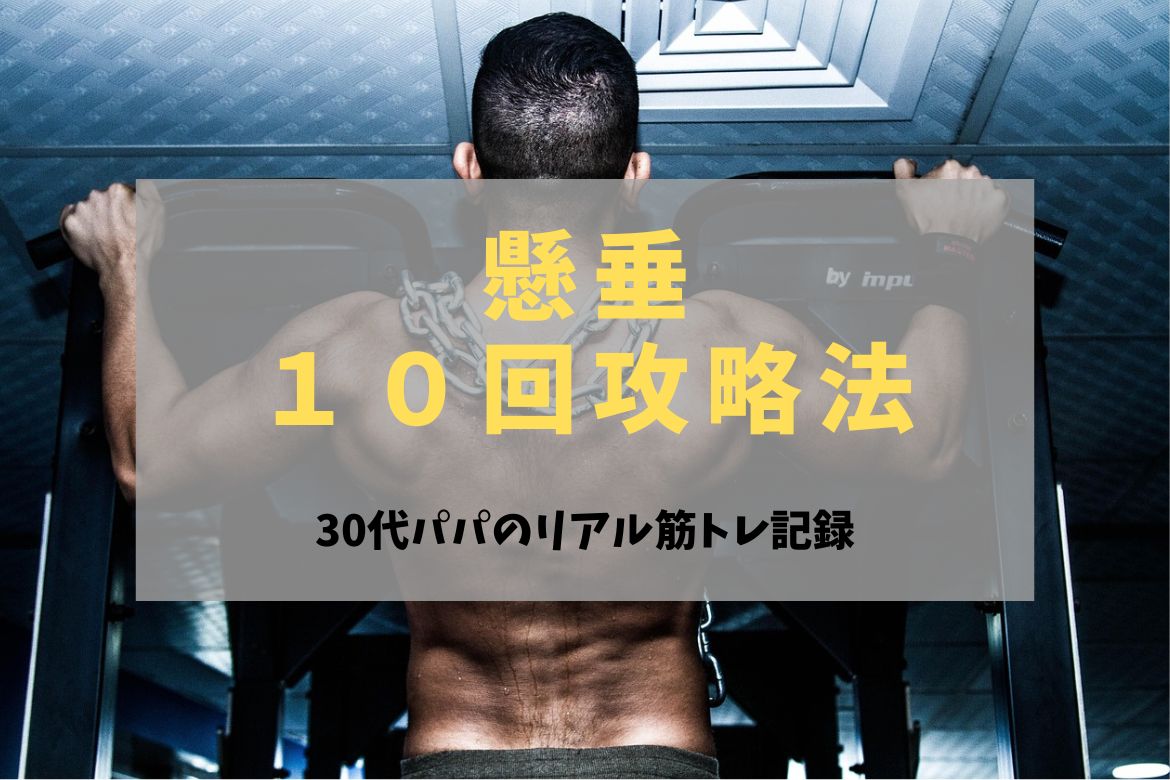



コメント