伸びない時期は必ず来る
懸垂を続けていると、誰もが経験するのが「停滞期」だ。
最初はゼロから1回、1回から3回、3回から5回と順調に伸びていく。
でも、ある時を境にパタリと成長が止まる。
- 何週間やっても回数が増えない
- フォームは崩れてないのに進歩がない
- 体重も変わってないのに同じ回数で止まる
ベルも懸垂7回から8回に伸ばすのに、1ヶ月以上かかったことがある。
「もう俺は限界なのか…」と落ち込んだ。
でも停滞期は成長の前兆でもある。
ここをどう突破するかで、その後の伸び方が決まるんだ。
停滞期が起きる理由
- 神経系が慣れてしまった
最初は「新しい動き」に体が順応するだけで回数が増える。
でも慣れてしまうと刺激が足りず、成長が止まる。 - 負荷が変わらない
いつも同じやり方・同じ回数では筋肉は驚かない。 - 回復不足
頻度を増やしすぎて疲労が抜けず、逆に力が出ないこともある。
停滞期を破る方法
1. フルレンジからハーフレンジへ
懸垂は「顎をバーにかけるまで」をフルレンジとする。
停滞したらあえて「半分だけ」を狙う。
- 下半分を繰り返す → 広背筋と握力を強化
- 上半分を繰り返す → 収縮の感覚を強化
普段とは違う刺激を与えることで壁を超えやすくなる。
2. 加重懸垂を取り入れる
「まだ10回できてないのに加重?」と思うかもしれない。
でも不思議なことに、重りをつけて3回やった後に自重に戻すと軽く感じる。
- リュックに重り(ダンベル・ペットボトル)を入れる
ベルはリュックにペットボトルを入れて加重懸垂をやった。
その後、自重で挑戦したら軽く感じて回数が伸びた。
3. 頻度を変える
- 週3でやってるなら週2に減らす
- 逆に週1なら週3に増やす
「筋肉を回復させる」か「神経系を慣らす」か。
停滞期には、このどちらかのアプローチが有効だ。
ベルは週3を週2にしたら、一気に疲労が抜けて次の挑戦で+1回できた。
4. グリップを変える
- 順手 → 逆手に変える
- ワイド → ナローにする
- タオルを巻いて握力に刺激を与える
グリップを変えると、普段とは違う筋肉が動員されて新しい刺激になる。
「いつもと同じ」から抜け出すことが停滞打破の鍵だ。
記録を取ることの重要性
停滞期を抜け出すために、ベルが一番やってよかったのは「記録を取ること」だった。
- 何回できたか
- どのフォームでやったか
- 体重は何kgだったか
- どんな疲労感が残ったか
これをノートやアプリに残すだけで、「なぜ停滞しているのか」が見えるようになる。
ベルも昔は「今日もダメだった」で終わっていた。
でも記録を取り始めてから、「3回目で息が乱れる」「週3より週2の方が伸びている」といったパターンに気づけた。
懸垂は回数が少ないからこそ、1回の差が大きい。
だから記録を残すことが、停滞突破の最大の武器になる。
ベルの停滞期エピソード
ベルが7回止まりだった頃、毎回同じ懸垂を繰り返していた。
「今日も7回。昨日も7回。先週も7回。」
正直、気持ちが折れそうになった。
そこで思い切って加重懸垂を取り入れ、同時に記録をノートに残した。
- 加重3kg → 3回成功
- 自重に戻したら → 8回成功
- その日の体重 → 71.8kg
- 次の日の疲労感 → 前腕パンパン
こうやって数字で見ると、「体重が軽いときに伸びやすい」「加重後は自重が軽く感じる」という法則が浮かび上がった。
停滞期を突破したのは、工夫+記録の力だ。
まとめ|停滞は見える化で破れる
懸垂の停滞期は誰にでも来る。
でも、それは「体が慣れただけ」。
工夫と記録を組み合わせれば、必ず次のステージに行ける。
- ハーフレンジで新しい刺激を入れる
- 加重で自重を軽く感じさせる
- 頻度を変えて回復か慣れを狙う
- グリップを変えて変化をつける
- 記録を残して自分の伸び方を分析する
停滞期は成長の前触れだ。
突破したとき、懸垂は一気に伸びる。
次回は「懸垂8〜9回の魔境に挑む」というテーマでいこうと思う。
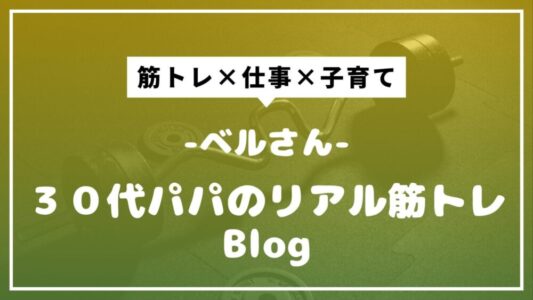
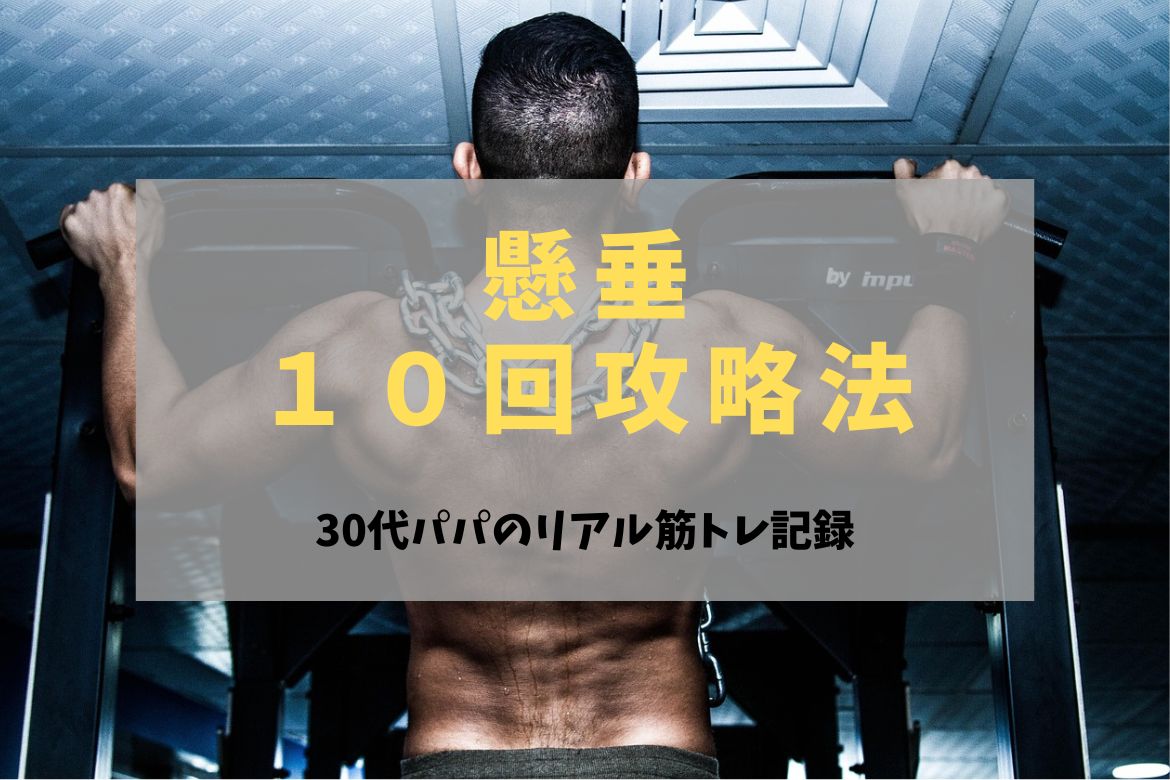



コメント